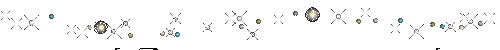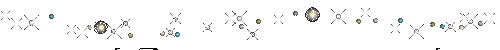――見上げれば月が在った。
只高く、美しく、そして何より孤独であった。
幼いながらに
――あぁ、アレには一生手が届かないのだろう
等と莫迦なことを想いながら、ぼんやりと上を見上げていた。
目に月は映っていない。只、捉えているだけ。
上を見上げれば嫌でも目に入ってしまう位大きな月だった。
ふと、手とお尻が濡れていることに今更気が付く。
何でそんなところが濡れているのか、不思議に思って少し考えた。
「・・・・・・あぁ、そういえば座ってたんだっけ?」
月が銀の光で照らす闇に呟いた。と言うよりも、
自分に問いかけてみた様な気がする。
――答えは出ない。出ないからもういい。考えるのも億劫だ。
いい加減、月もこんなに高くなってる。そろそろ帰らないと。
感覚のない足で立ち上がった。帰るのも良いのだが、足場が悪く歩き辛い。
ここに来る前に通った森も、悪趣味な赤いカーテンなどぶら下げてよく見えない始末。
辺りは銀の光が神々しく降り注いでいて、
地面に転がる邪魔なモノを照らしているのに・・・・・・この周りだけ暗い。
この場所を中心に赤黒い地面が揺らめいている。
まるでここから闇が滲み出て、銀の光にも嫌われたように。
そう思うと少し悲しくなった。
今日はもう、ここまで一緒に来た子を見つけて一緒に帰ろう。
でも、あの子は探すのが少し難しくなった。
バラバラになってるからドレがあの子の体か判らないから。
|
|